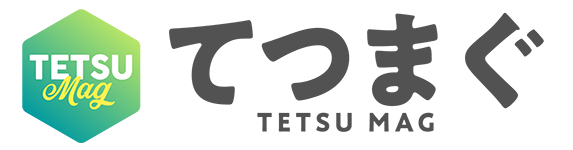横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒
一級鉄筋技能士
唎酒師
狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中
建設業では「あいつはセンスが無い」と理不尽に評価されることが非常に多いです。
この記事では、建設業における「センス」とその鍛え方について解説します。
目次
日本の建設業特有の組織文化・慣習
日本の建設業には職人文化が深く根付いています。
職人文化とは、伝統的な職人による高度な技術と専門知識を重視し、職人の技術や職業を尊重する文化を指します。
日本の歴史や文化には、建築や工芸など様々な分野において職人が重要な役割を果たしてきました。
職人文化について詳しく見ていきましょう。
職人の特徴は精密さと高い美意識
「職人」と呼ばれる熟練者たちは長い修行と経験を積み重ね、特定の技術や職業を身に着けてきました。
熟練者たちは、細部にまでこだわる精密さと高い美意識を持っており、自らの技術に誇りを持ち、職業としての使命感を持って作業に取り組みます。
自らの手で創り出した製品や建築物に対する責任感も強いです。
若手技能士は「センス」を持ち合わせていないと理不尽に怒られる
建設業は深刻な人材不足に陥っているので、外国人実習生に頼らざるを得ない状況です。
「センス」を持ち合わせている熟練者は、一切経験を持たない外国人実習生に対して容赦なく指導し、「センス」を持ち合わせていない若手は理不尽に怒られることになります。
この原因は以下の通りです。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
1.熟練者の期待のギャップ 人はそれぞれ異なるバックグラウンドや経験を持っており、美的感覚や判断力にも個人差があります。 熟練者が持つセンスと、若手のもつセンスに大きなギャップがある場合、理不尽に怒られることがあります。 2.コミュニケーションの不足 センスは主観的な要素が強いため、自分の考えを相手にうまく伝えることが難しい場合があります。 コミュニケーションが不十分であると、相手の期待に応えることができず、理不尽に怒られることがあります。 3.環境や文化の違い センスには文化や環境による影響もあります。 異なる文化や環境で育った人同士が交流する場合、センスの違いが理解されず、誤解が生じて怒りの原因になることがあります。 4.パーソナルな感情やプレッシャー センスに関わることは感情や個人的な意見が絡むことが多いため、相手が感情的になったり、自らのプレッシャーを相手に向けてしまったりすることがあります。 |
「センス」はとても重要なものですが、人材不足が深刻な状況下では人材確保を難しくしてしまう大きな要因にもなっています。
建設業におけるセンスについて

熟練者が言う「センス」とはいったい何なのでしょうか?
建設業における「センス」は、技術や知識だけでなく、経験や感覚に基づく洞察力や判断力を指します。
建設業は、建物やインフラの設計、施工、改修など、複雑で多岐にわたる作業が必要な分野であり、単なる技術的な能力だけではうまくいかない事が多々あります。
センスとは「モノや人に対する几帳面さ」を指す
「センス」は以下の6つの要素に分けることができます。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
1.デザインセンス 建物や構造物のデザインにおいて、美的なバランスや見た目の良さを判断する力です。 機能性だけでなく、美しさや調和を考慮して設計することが求められます。 2.技術的センス 建設における専門知識や技術を駆使して、問題を解決したり、効率的に施工したりする能力です。 経験に基づく的確な判断が必要です。 3.経験的センス これまでの経験から培われた知識や洞察力により、計画や施工の段階で予想される課題やリスクを早期に発見し、対応策を講じる力です。 4.客観的センス 建設プロジェクトは多くのステークホルダーが関わるため、利益調整やトラブル解決など、客観的な視点から全体のバランスを取る能力が求められます。 5.タイムマネジメントセンス プロジェクトのスケジュールや進捗管理を的確に行い、計画通りに進める能力です。 6.チームワークセンス 建設プロジェクトは多職種のチームが協力して進められることが一般的なので、協調性やリーダーシップを発揮し、チーム全体のパフォーマンスを高める力が重要です。 |
小難しく書いてありますが、要は「モノや人に対する几帳面さ」と言い換えることができるでしょう。
例えば、外国人実習生に「帰宅する前に休憩所を掃除してから帰宅するように」とざっくりとお願いしたとします。
「机の上の缶ジュースの空き缶、机の上のホコリ、フロアの土汚れ、タバコの吸い殻を綺麗にしてから帰宅するように」と指示すれば分かりやすいですが、このように思わずざっくりとした指示になってしまうのはアルアルの現象ではないでしょうか。
豊富な勤務経験を持った30代前後の技能実習生の方であれば、机の上の缶ジュースの空き缶、机の上のホコリ、フロアの土汚れ、タバコの吸い殻を、客観的にも主観的にも納得のいくレベルで片づけることができます。
一方、20前後の勤務経験が無い技能実習生は、机の上の缶ジュースの空き缶を片づけて終わりにしてしまうでしょう。
時間に対しての考え方についても、普段からmm単位で管理している熟練者にとって1分単位で時間を管理するのは当たり前の行動です。
5分単位、10分単位で今まで行動していた若手にとって、1分単位で行動を管理できるようにするのはとても労力が要ることでなかなか身に着けることはできません。
「センス」を磨くには1年以上の訓練、経験の蓄積が必要
休憩所の掃除ならできなくても簡単にフォローできますが、それが取引先に納品する商品の場合は話は別です。
鉄筋工事業であれば、納品する商品をmm単位で管理する必要があります。
納品検査前には、型枠内に落ちている番線クズや使用した絵符、自動結束機の使用後の玉、不要な鉄筋等を回収しなければなりません。
真夏の酷暑の中、熟練者からのざっくりとした指示に対して熟練者が納得できるレベルの仕事をするのはとても大変なことです。
「センス」を磨くには個人の能力や経験、学習スタイルなどによって異なりますが、一般的には以下の点を考慮する必要があります。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
1.経験の蓄積 センスは、経験から発展することが多いため、時間をかけて実務経験を積むことが重要です。 建設業においては、多くのプロジェクトに携わることで、問題解決や判断力が磨かれます。 2.学習と専門知識の習得 建設業は技術や法規制が頻繁に変化する分野です。 学術的な知識や最新の技術に常にアクセスし、学び続けることが必要です。 3.メンターの存在 経験豊富なメンターから指導を受けることで、短期間で成長することができる場合があります。 メンターからのフィードバックやアドバイスは、センスを高める上で非常に有益です。 4.自己改善と反省 継続的な自己評価や反省を行い、自己改善に努めることも重要です。 失敗から学び、改善していく姿勢がセンスの磨きにつながります。 |
建設業では、「4.自己改善と反省」「2.学習と専門知識の習得」が特に重要になります。
熟練者は若手技能士に対して優しくサポートすることはほとんどありません。
重要なのは、焦らずコツコツと学び、経験を積んでいくことであり、現場以外の場所で気づきや経験の回数を増やすことだと考えます。
時間と努力をかけることで確実にセンスを磨くことができるようになりますが、一人前と評価されるには1年以上の時間が必要になるでしょう。
メンターを頼るのではなく、自己改善と反省が重要
まとめ
この記事では建設業における抽象的な概念「センス」について解説しました。
「センスが無い」と言われたとき、自分に何が足りなかったのか自己改善と反省を繰り返して少しずつセンスを磨いていきましょう。